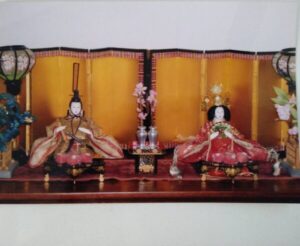半夏生
四季のしつらい初夏の頃、裏庭の日陰で白く色づいた半夏生の花が咲きます。半夏生は、植物としても知られていますが、暦の上で雑説の1つでもあります。二十四節気、五節句などの他に、日本独自の繊細で移ろいのある季節をより正確に把握するために作られた特別な暦日です。人々は、それを日々の生活の目安にしてきました。ほかにも、八十八夜、入梅、土用などがあります。農業や漁業は、季節や気象に左右されることが多く、雑説により時期や節目を正確に見極める必要があったからです。夏至から数えて11日目となる7月2日頃から七夕(7月7日)までの5日間を示します。農家では田植えや養蚕などを兼業することも多く、半夏生までに田植えを終えるという目安になっていたようです。また地方によっては、この時期に疲労回復効果のあるタコを食べると良いとされているようです。