寒蝉鳴(ひぐらしなく)
四季のしつらい立秋の次項となり、蜩が鳴き始めるという意味です。ヒグラシよりもツクツクボウシの方が後に鳴くことが多いのですが8月中旬には両方鳴き出します。ヒグラシは、涼しげな高い声でカナカナと。寒蝉は、ツクツクボウシをさしていたのではないかと言われています。今年は、猛暑で蝉たちもさすがにどこかに行ってしまったのか、庭の木々から聞こえてくる、大合唱の日もあまりなく過ぎています。

立秋の次項となり、蜩が鳴き始めるという意味です。ヒグラシよりもツクツクボウシの方が後に鳴くことが多いのですが8月中旬には両方鳴き出します。ヒグラシは、涼しげな高い声でカナカナと。寒蝉は、ツクツクボウシをさしていたのではないかと言われています。今年は、猛暑で蝉たちもさすがにどこかに行ってしまったのか、庭の木々から聞こえてくる、大合唱の日もあまりなく過ぎています。

蓮は日本だけでなくアジアで広く見られる水生植物です。蓮の花は朝早く、まだ薄暗いうちから花がゆっくり咲き始めます。そして午前中には完全に開花し、昼過ぎには再び閉じ始めます。このサイクルを数日繰り返しながら、花は散っていきます。自然の神秘的なリズムを感じます。数年前に朝、蓮の咲く池に見に行きました。自然の移ろいとその美しさに清らかな思いになりました。
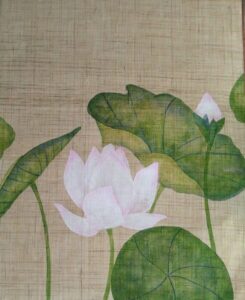
旧暦の六月、夏越の祓(なごしのはらえ)があります。茅で作られた輪をくぐって一年の前半を無事に過ごせたことを感謝し、残りの半年も健康に過ごせるようにと願う日本の行事です。室町時代の宮中では夏の暑い時期に、氷室の氷を掘り出しひとかけらを口にし暑気払いをしていましたが、氷が食べられない庶民が、氷のかけらに似せた三角のお菓子(水無月)を食べたのが始まりと言われています。

庭仕事をしながら、ミミズに出会うとうれしくなります。それはミミズは土を耕すことが知られているため、ここは豊かな土壌なのだと思うからです。日本では、自然の鍬と言われてきました。古代ギリシャのアリストテレスはミミズを「大地の腸」と名づけていたとか。進化論で知られるダーウィンも晩年はミミズの研究に捧げ、ミミズがいかに土壌を作るかを長年観察したようです。雨の後など、石畳にでてきます。うっかりしていると、鳥に見つけられて、食べられてしまいます。ミミズは、腐葉土を食べ、窒素やリンを含んだ栄養豊富な糞を排出しています。その糞は、小さな微生物たちの格好の住処となり、さらに分解されて肥沃な土を作ると学生時代の土壌調査の研究で学びました。健康な土には、1グラム中に1億もの微生物がいるといわれています。ミミズが動き回ることによって、土中に酸素がゆきわたり、通気性がもたらされ、ふかふかの土を作ってくれるミミズの働きは、大きいのです。

牡丹は晩春から初夏に向けて咲き、花は20日ほど楽しめます。1つの花が10~20センチと大きく花びらが幾重にも重なり、風に揺れる花は非常に美しい佇まいを観せます。牡丹と芍薬は似ていますが、花の咲く時期は牡丹が4月半ばから5月初旬頃、芍薬は初夏。そして葉の形状は、牡丹の葉は艶がなく葉先は大きく広がりギザギザしており、芍薬の葉は全体に丸く艶があるなどの違いがあります。牡丹は、花びらがひらひらと散り、芍薬は椿のように花ごと落ちます。花の香りは、牡丹はほんのりと、芍薬は優しい香りがします。(須磨離宮公園にて牡丹の花を写生中)

遠くの空で雷が鳴りだす頃。春の雷のほとんどが寒冷前線の通過によって起こります。テレビの報道を見ながら驚きますが、雪やひょうが降ることもあります。ようやく暖かくなってきたと思っていたのに、まだまだお天気は定まりませんね。この時期を過ぎれば春爛漫といった穏やかな日々が訪れます。雷の語源は、神鳴りで鬼の姿で背中に太鼓を背負い、それを打ち鳴らす雷神の絵を目にします。雷が多くなる春から夏はちょうど稲が育つ時期で、雷も稲の生長に影響するそうです。季節が少しずつ前へとすすんでいる時期です。
